金融教育フェスタ
金融教育フェスタ2019
先生のための金融教育セミナー

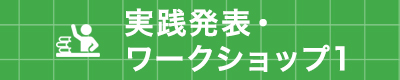
「市場体験型シミュレーションゲーム
『Market Game』の開発と実践」
(小学校3~6年、社会)
講 師
山梨学院小学校
鈴木 崇 教諭
【進行・コメント】 玉川大学教育学部 樋口 雅夫 教授
<実践発表>
『Market Game』は、金融教育の中のキャリア教育に重点を置いた実践で、小学校の中学年から高学年を対象に実施しています。子どもたちが仲間と一緒に会社を起こし、それぞれの状況下で次々と起こるイベントを乗り切っていきます。その過程で、自己発見力や問題発見力、マネジメント力やリーダーシップ、企画・開発力といった能力を育成することを目指しています。
『Market Game』を始めたときに心にあったのは、自分の将来や夢を簡単に諦めてほしくない、自分の力で困難を突破していけるような大人に育ってほしいという思いでした。このゲームを効果的に行うには、低学年の段階での土台作りが重要です。当校では、地元の企業と連携し、ケーキやきなこを使った商品など、企業に新しい商品開発を提案する体験学習を行っています。コンペでプレゼンテーションをして選ばれれば、自分たちのケーキが本物になるので、子どもたちも真剣です。1個も商品化されない年もあって、子どもたちがみんなで泣きじゃくることもあります。3年生では模擬商店街に取り組みます。3年生が店員で、その他の学年がお客さんです。5、6年生から時に厳しいアドバイスを受けながら心を込めて商品を作ります。
こうした体験学習を通して「良いものを作って喜ばれると嬉しいな」、「働いて対価をもらうこと、社会貢献することって楽しいな」と感じとってもらってから、中、高学年で『Market Game』に入ります。まず社長や販売部長、開発部長などの役割分担を自分たちで決めます。この活動の中で、仲間がいることの大切さも伝わると考えています。また、このゲームでは、私物の筆記用具などは一切使えません。必要なものは対価を払って手に入れるしかありません。お金の価値、鉛筆一本のありがたみをわかってもらうためにそのように設定しています。
『Market Game』は、必ず振り返りを入れながら進めます。最終的には、一番多く稼いだ会社が勝ちということになりますが、振り返りの中でその会社が稼ぐことができた理由をみんなで考えます。勝ったチームに対して「せこい」という声が上がることもあります。そこから「お金だけあっても駄目だ」、「信頼や名誉も大事」、「お金、お金というのをやめたい」というような声も聞こえてきます。このゲームの良さはまとめると3つあります。自分や友だちの良さを知ることができること、世の中の仕組みを学ぶことができること、社会の中で生きる実践力を高めることができることです。さらには、「算数の勉強に役立った」、「国語で勉強した敬語がうまく使えて嬉しかった」というような感想も聞かれました。金融教育が教科学習にも活かされている実感を得られたことも嬉しく思っています。
<ワークショップ>
ワークショップでは、市場体験型シミュレーションゲーム『Market Game』を実際に体験していただきました。オリンピック会場を作る建築資材の会社という設定で、グループごとに様々な条件下で商品を作り、売上げを増やすための工夫を考え、充実したワークショップとなりました。
鈴木先生からは、「英語でしか対応しない時間を設けるなど、コミュニケーション能力を高めたり、思い通りにいかない経験を積ませる工夫もしています」とお話があったほか、「本校の金融教育では、全領域を挙げて、皆でつながっていこうとしています。皆さんの学校でもぜひ複数年にわたって、縦のつながり、横のつながりを強化しながら実践を積み重ねていただければと思っています」と述べられました。
<コメント>
樋口雅夫先生より、次のようなコメントがありました。
鈴木先生の『Market Game』は、まさに子どもたちの関心・意欲が高まる教材であると思います。小学生には少し難しいのでは、複雑すぎるのではと思われた方もいらっしゃるかもしれません。しかし、このゲームを通して小学校の段階で新たな発想や構想に基づいて財・サービスを創造する過程を体験することができるわけです。これは、中学校の学習指導要領に書かれている起業に関する説明です。それを小学生が試行錯誤しながら、楽しみながら作り上げていくことこそ、主体的な学びであろうと思います。まずは、この『Market Game』を取り入れてみて、子どもたちがこの活動の中で学ぶことがどの目標や教科に位置付いてるかを整理していくと良いのではないかと思います。
鈴木先生はこの実践を10年間にわたって行われ、その成果を今日発表してくださいました。カリキュラムマネジメントのPDCAサイクルを回していく中で少しずつ充実した内容になってきたのだと思います。本日ご参加の先生方も、10年後、20年後に向けてこの実践を参考にしていただければと思います。

実践発表・ワークショップ1の模様
- 主催:金融広報中央委員会、鳥取県金融広報委員会
- 後援:文部科学省、金融庁、消費者庁、日本銀行、日本PTA全国協議会、鳥取県、鳥取市、米子市、 鳥取県教育委員会、鳥取市教育委員会、米子市教育委員会、鳥取県小学校長会、鳥取県中学校長会、鳥取県高等学校長協会






























































