金融教育フェスタ
金融教育フェスタ2019
先生のための金融教育セミナー

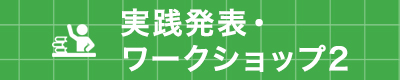
「アントレプレナーシップにおける金融教育
~東和中学校のアントレプレナーシップの実践報告~
(中学校2年、総合的な学習の時間)」
講 師
元周防大島町立東和中学校教諭
西村 仁明 氏
【進行・コメント】 玉川大学教育学部 樋口 雅夫 教授
<実践発表>
東和中学校におけるアントレプレナーシップの実践は、販売実習を通して起業に必要な技能や人との関わり方を身に付け、精神的にも経済的にも自立した未来を担う若者を育成するプログラムとして取り組んできました。
なぜ起業に目を付けたかといいますと、東和中学校がある周防大島町は人口が減りつつある一方で高齢化が進んでいる地域です。また、子どもたちの中には、人間の労働が今後、人工知能やロボットに置き替えられると聞いて、将来の夢を持てなくなっている子もいます。そこで、地域と関わり合いながら、チャレンジ精神を持った子どもたちを育てたいと考えました。また、この実践は総合的な学習の時間で取り組んでいるものですが、本校では、総合的な学習の時間に、周防大島出身の民俗学者、宮本常一の「あるく」、「みる」、「きく」の手法を取り入れ、さらに表現する力、発表する力も重視しています。
実践の流れをご説明します。最初にオリエンテーションで仮想の会社を設立します。そして、市場調査を行い、経営戦略を練って必要資金を算出します。株主募集集会を開催し、仕入れ、販売実習を行って、最後に会計監査、株主総会を行うという流れです。市場調査は、販売実習を行う道の駅で、どのエリアからお客さんが来ているか、年齢層はどうか、どのような商品やサービスを必要としているかなどを調べます。一番の山場は株主募集集会ですが、そこに至る前に発表の場をいくつも設けています。東和中学校は中高一貫校なので、高校生を前に発表してアドバイスをもらったり、講演に来ていただいた地元の企業の方に発表を聞いてもらったりして表現力を磨きます。必要な資金を算出するにあたり、直接お店と交渉したりもします。必要資金を得るために、いよいよ株主募集集会で保護者や地域の方々に向けてプレゼンテーションを行い、1株500円で株主を集めます。最近では、株主を募集する前に必要となる資金について、東和中学校のコミュニティスクールを銀行と見立ててそこから借りるというシステムも取り入れました。販売実習の後は会計監査を経て、株主総会での会計報告を行います。株主には原資のほかに売り上げから配当金を出して返金します。人件費にあたる部分は社会貢献として周防大島町へ寄附しました。
こうした活動は、毎年継続して行うことが大切だと考えています。東和中学校でこのような活動を続けられる理由は、小規模校だからということもあると思いますが、コミュニティスクールとの関わりが大きいと思います。教員には人事異動がありますが、コミュニティスクールのキャリア教育デザイナーがいることで、継続的な実践ができていると思います。
<ワークショップ>
ワークショップでは、グループに分かれて、経営戦略の立案と株主募集のためのプレゼンテーションを行いました。郷土料理や地域の特産品を意識した商品を提供する会社、地元の街を巡るスタンプラリー形式のゲームを販売する会社などの設立案を練り、必要資金や想定される利益、株主に還元できる金額を算出して、プレゼンテーションに臨みました。
最後に西村先生は、「東和中学校がある周防大島町は、都会と比べて子どもたちが本物に触れる機会が少ないです。この実践は、子どもたちに失敗を経験させること、本物に触れて本物を体験させることで生きた教材になっていると思います」と述べられました。
<コメント>
樋口雅夫先生より、次のようなコメントがありました。
西村先生のお話にあった通り、本物に触れさせるという点がポイントだと思いました。この実践では中学生が実際に商品を作り、本物のお金が動きます。学校教育において、子どもたちが本物に触れる体験をすることはあまり多くないのが現状ですが、その理由は時間が足りないことと、本物に触れさせるためのノウハウが不足しているということではないでしょうか。この実践は、ねらいを明確にして地域の方に協力を仰ぎ、教科の時間ではなく総合的な学習の時間を使って行ったことで、その二つの課題を見事に解決した実践であったと思います。子どもたちにとっては、地域の方から預かったお金を使うとなると、損を出してはいけない、利潤をあげなければ、ということになると思います。それが現実であり、この実現可能性を究極まで追求できる学習が、アントレプレナーシップ教育であろうと思います。
このような実践をどこまで自校でできるだろうかと思う先生方もいらっしゃると思います。初めから大きなことをしようとするのではなく、まず一歩を踏み出して、地域の調査を行うということから始めるのでもよいと思います。先生方は異動することもあるわけですが、地域の方々と連携することで、地域の方から後押しされて活動が続いていくこともあると思います。できるところからスタートをし、子どもたちが本物に触れる学習を取り入れることが大切だと私も学ばせていただきました。

実践発表・ワークショップ2の模様
- 主催:金融広報中央委員会、鳥取県金融広報委員会
- 後援:文部科学省、金融庁、消費者庁、日本銀行、日本PTA全国協議会、鳥取県、鳥取市、米子市、 鳥取県教育委員会、鳥取市教育委員会、米子市教育委員会、鳥取県小学校長会、鳥取県中学校長会、鳥取県高等学校長協会






























































