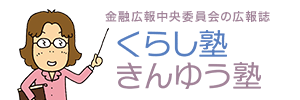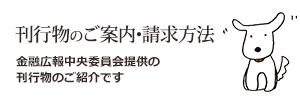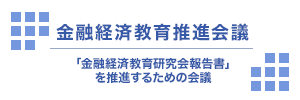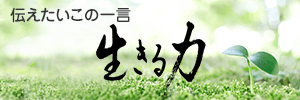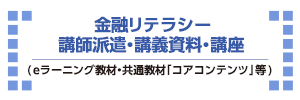著名人・有識者が語る ~インタビュー~
自分で限界を決めたことはない だから続けられていると思います
プロサッカー選手 中村 憲剛
Jリーグ川崎フロンターレの中心選手として、10年以上にわたりチームをけん引してきた中村憲剛選手。
壁にぶつかるからこそ考える。
続けることがチャンスを生む。
「好き」を仕事にすることへの道のりや思い、長年続けている社会貢献などについてうかがいました。

中村 憲剛
(なかむら・けんご)
プロサッカー選手。J1川崎フロンターレ所属。1980年生まれ。東京都出身。小学1年生でサッカーを始め、府ロクサッカー少年団、都立久留米高校、中央大学を経て2003年川崎フロンターレに入団。2006年日本代表に選出。2014年から2017年1月までチームキャプテンを務める。2016年にはJリーグ最優秀選手賞を獲得。著書に『サッカー脳を育む』(ぴあ)、『考える習慣』(ベースボール・マガジン社)、『心をつなぐボール』(あかね書房)ほか。
「考える力」を身に付けて憧れのプロの世界へ

中村選手が中学1年だった1993年に、Jリーグが開幕。多くのサッカー少年と同じようにJリーガーに憧れていた中村少年でしたが、中学・高校時代を過ごしたのは全国的なサッカー強豪校ではありませんでした。中学生の頃には1年間サッカーから離れた時期もあったと言います。体格はとても小柄で、足が速いわけでもなく、進学などで新しいチームに加わるたび、周囲との実力の差に愕然としたそうです。
そんな中村選手が、プロ入りし、日本代表選手にも選ばれ、2016年にはJリーグMVPを獲得。このような栄光を勝ち取るまでに、どんな努力をしてきたのでしょうか。
「とにかくボールを蹴るのが好きで、サッカーがうまくなりたいという一心でやってきました。今でももっとサッカーがうまくなりたいと思いますよ。ただそれだけです」。
中村選手は、その時々に自分をしっかり分析し、やると決めたことを実行してきたことで、次へ、その次へと道が開けてきたと振り返ります。
「サッカーは体格差が能力差になって出るスポーツですから、小柄でも、足が遅くても、それをどういう方にもっていけばいいのか、小さな頃から常にそうやって考えていました。だから、『考える』という習慣が身に付きました。体格や身体能力に恵まれていたら、そんな機会はなかったかもしれません」。
今の自分に足りない技術、どうしたら試合に出られるか、監督やチームメイトが自分に望んでいることは何かを考える。そうやって「考える力」を身に付けてきたため、それなりに身長が伸び、体も動かせるようになったときに、できることの幅が一気に広がったと言います。
中村選手でも、サッカーをやめたいと思ったことがなかったわけではありません。「人間は弱いものだし、ときには逃げることもあるけれど、また元の挑戦に戻れるかどうかが成否の分かれ目」。だからこそ、壁にぶつかって挑戦を諦めようとしている子どもたちに対して、「自分で自分の可能性を閉じないでほしいと思いますね。自分は今、どういう壁に、なぜぶつかっているのか、乗り越えるには何をしたらいいのか。そのように考えて行動することで必ず道は開ける。そして1日1日を積み重ねていくことが、何か大きな決断やチャレンジをしなくてはいけないときの準備になると思います」と、中村選手は自らの子どもの頃を振り返りながらエールを送ります。
好きを仕事にし、続けていくこと
小さな頃から憧れていたJリーグの舞台に立ち、プロとして大観衆の中でプレーをし始めた頃は、責任を感じ、怖さを覚えたという中村選手。「ただ、それ以上にわくわく感がありました。自分のワンプレーでお客さんが沸いたり感動してくれたり。それはもう、何ものにも代えられない、この仕事の素晴らしさ。試合に勝ったときは、もうこのまま時が止まればいいって思います」。
好きなサッカーを仕事にできた、こんな幸せなことはないと話しながら、「だけどお金のことを考えてサッカーをしたことは今まで1度もない」。年俸を上げたいからがんばろうと思ったことはなく、目の前の課題をこつこつとこなすことでレギュラーの座を勝ち取り、チームが勝つために必要なことを考えてプレーした末にチームはJ1昇格、さらに自分自身は日本代表にも選ばれた。努力の結果としてお金は後からついてきた。「その順番を1回も間違えたことはないですね」。
でも、好きなだけでプロになれるものなのでしょうか?「〝好き度〞は誰にも負けていないっすよ! その結果プロになれた」ときっぱり。「好きだから、もう自分にはできないとかダメだとか思ったことはない。かといって自信満々だったわけでもない。〝好き度〞で、苦手なことに対して努力する程度は変わってくる。好きだから、ただただ努力をし続けてきた結果です」。
さらに、プロになった後は試合に出場し続けなければなりません。「いくらサッカーがうまくても、人の話を聞けなかったり、プライドが高すぎたり、ときに自分を曲げることができなければ、試合に出してもらえずプロの世界で生き続けることは難しい」。だから、「プロで続けていくためには、この裏を返せばいいんじゃないかな。素直であった方が絶対いいと思うんですね」と中村選手。「みんな小さい頃からサッカーが上手で、プライドをもった人のピラミッドの頂点がJリーグの選手たちです。そんな人たちの中から日本代表に選ばれて集まった選手は皆、素直でした。話を聞くし、研究熱心で自分にいいことはどんどん取り入れようとしていました。すごく貪欲だった」。
「これって、どんな仕事でも一緒ですよね」と続けます。「やりたくない仕事もあるでしょう。でも、それもやって自分の幅を広げればチャンスは巡ってくる。〝僕にはこれは、できません〞とか言ったら使われないじゃないですか。思った通りに人生が運ぶことなんてそうそうないから、自分でやりきったと思えるよう、毎日悔いのないようにやっているつもりです。努力なんか天井知らずですね」。
スポーツ選手だからこそできる社会貢献活動の輪を広げる
プライベートでは一男二女の父、サッカー界きってのイクメンとしても知られる中村選手。サッカー以外に力を入れているのが、子どもの虐待やいじめを防止するための活動です。川崎フロンターレの選手として、児童虐待防止のポスター撮影に協力したのがきっかけでした。まもなく長男を授かり、虐待やいじめでかけがえのない命が失われているニュースにそれまで以上に心を痛めるようになります。心に深い傷を負っている子どもの命を救うため、何か自分にできることはないだろうか。周囲にも相談し、2012年に非営利法人「チャイルドワン」を立ち上げ、子どもを守る傘となる「ピンクアンブレラ運動」を展開します。
中村選手はホームページ上の動画で、子育てに悩む親、周囲の大人、いじめを受け苦しむ子ども、いじめている子ども、それぞれに向かって、真摯な言葉で話しかけています。児童養護施設を訪問したり、施設の子どもたちを川崎フロンターレの試合に招待する活動もしています。
「ほそぼそとだけれど、自分の活動の柱としてやらせてもらっています。サポートしてくれる人も増えてきて、イベントなどもできるようになりました」。悩んでいる子どもたちが1日でも楽しく過ごしてくれれば、あるいはサッカー選手を目指すなど何か熱中できるものを見つけてくれればと期待します。「残念なことに虐待やいじめのニュースは絶えないし、自分の活動ですべてが解決するわけではないと思うけれど、自分を通していろんな人が手をつなぐことで活動の輪を大きく広げることができると思います」。
そのほか、東日本大震災の被災地に向けては、震災直後から1ゴール、1アシストごとに10万円を義援金として送ることを続けています。川崎フロンターレとして被災地への支援を続けるなかで、最初は自分に何ができるのかと不安があったものの、サッカークラブやJリーグができること、そのパワーを体感したのだと言います。
「サッカー選手だからこそできるっていう思いはあります。まずは人々にこの問題へ関心をもってもらうことが大事。ああ、憲剛がこんなこと言っている、しているってみんなに知ってもらって、そこから活動が広がれば、虐待やいじめに苦しんだり、自ら命を断とうと思っているような子どもを、1人でも減らせるかもしれない。また、東日本大震災の被害を思い出してもらえれば。スポーツ選手として、少しは注目してもらえる位置に自分はいると思います」。現役の選手なのでこの活動に割ける時間の制限はあるけれども、「そのなかでできる限りのことをやっています。こうした活動をライフワークとして続けていきたい」と、中村選手は力を込めます。

主将のバトンを次に渡し、プレーヤーとして前進し続ける
この1月、中村選手は3年間務めた川崎フロンターレの主将を小林悠選手に引き継ぎました。主将時代は、自分自身が学生時代から「考える力」を身に付けてきただけに、チームメイトにあれこれ指示を出すのではなく、プレーで皆を引っ張り導きたいという思いが強かったと語ります。主将を退いた現在は、今までとは違い、一歩引いた立場でチームを観るようになりました。
「主将になって初めて考えることっていっぱいあるんですね。悠もこの半年ちょっとで随分変わりましたし、僕自身もそうでした。悠は僕の背中を見て、学ぶところも反面教師にするところもあると思う。また悠の背中を見て次の世代が成長していけばいいんじゃないかな」。
インタビューの最後で、遠い先のことはあまり考えていないという中村選手に、自分について今いちばん考えていることは?と聞いてみると「次の試合に勝つこと!」と即答。「今自分がやれることを全力でやるのが嬉しくてしょうがない」。中村憲剛選手の前進は、今までも、これからも止まることはありません。
「サッカーが楽しくて仕方がないですね。やめられないっすね」。
![]()
本インタビューは、金融広報中央委員会発行の広報誌「くらし塾 きんゆう塾」vol.42 2017年秋号から転載しています。