金融教育公開授業
平成21年度金融教育公開授業(全国リレー講座)
福岡県金融広報委員会
小郡市立大原小学校
金融広報中央委員会
福岡/小郡市の実施報告
「金融教育公開授業 in 福岡(大原小学校)」(11月6日開催)
小郡市立大原小学校は、福岡県金融広報委員会より金融教育研究校(20-21年度)の委嘱を受け、研究主題を「ものやお金を大切にする 心豊かな子どもの育成~大原プログラムに基づいた体験活動を通して~」とし、各教科・道徳・学級活動・総合的な学習の時間を中心に地域と関わりながら金融・金銭教育の視点を取り入れた授業に取り組んでいます。
▼ 参加者内訳:
1.公開授業
全学年、全クラスを対象とした公開授業では、低学年ではものやお金の大切さに気づくこと、中学年では、限られたお金・もの(資源)を有効に使うことができ、感謝の気持ちを持ち働くことができること、高学年では、労働の尊さに気づき、進んで働く、お金やものを計画的に使うことができ、金融・金銭の簡単な仕組みが分かることをめざして各学年、発達・経験に踏まえて学校独自のプログラムを取り入れた授業を実施しました。
(1) ものをたいせつに「あおい じてんしゃ」(1年生 道徳)
お下がりの青い自転車を使っていた主人公が新しい自転車を買ってもらえることになるが、まだ使える自転車が処分されることを知り、お下がりの自転車を使い続けるという話を題材に、主人公の揺れ動く気持ちを演技しながら、ものを大切にすることについて考えました。また、6年生が1年生の時から大切に使い続けている筆箱とその思いを紹介し、ものを最後まで大切にすることが1年生にもわかったようでした。
(2) 「町で生活し、働く人とのつながりを考えよう」(2年生 生活)
生活につながりの深い「パン屋さん」に焦点をあて、パンの作り方や作業過程を調べ、自ら作り、売る・買う場面を両面から経験させることにより、ものを作る人の苦労や工夫、生活する人にとっての上手なお金の使い方を考えました。
(3) 物を大切に「えんぴつは なんさい」(3年1・2組 道徳)
学校でのたくさんの落し物に目を向け、日頃何気なく使っている1本の鉛筆も、その軸は70年以上たった木からできていること、たくさんの人の労働に支えられていることを理解し、ものを大切にしようとする気持ちを学びとしました。
(4) 「もったいない 上手なお金の使い方を考えよう」(3年3組 学級活動)
給食の残菜を調べたり(温食・おかず・パン・ご飯・牛乳について)、給食センターの方を招いて残菜の量や金額についての話を聞いたりして、作る人の思いや、残菜をお金に換算することで家の人が払った給食費を無駄にしていたこと、もの=お金であることを理解するとともに、感謝の気持ちを持つことができました。
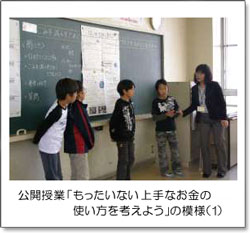
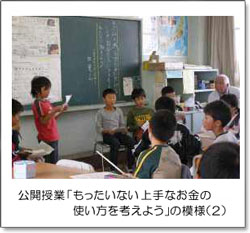
(5) 「ごみ減量・エコアップ大作戦」(4年生 総合的な学習の時間)
身近なごみ調べから小郡市のごみ問題に広げ、ごみを少しでもなくすために、リデュース(発生抑制)、リユース(再利用)、リサイクル(再生使用)の視点から実際に牛乳パックや新聞紙の再利用、廃油からの石鹸作り体験等を通じて、自分たちにできること、これからの課題、伝えたいことを発表しました。
(6) 「食と食をとりまく環境を考えよう~食は田んぼにあり~」(5年生 総合的な学習の時間)
私たちの食生活にもっとも深く関わる「お米」について種まきや稲刈り等を体験し、農業に携わる人の思いや生き方、収穫の喜びを経験しました。公開授業では、お世話になった人や地域の人に自分たちの学習したことや感謝の気持ちを伝えるためにグループに分かれてa)「販売試食会」b)「米の販売」c)「感謝集会」の計画を立てました。
(7) 「金銭や物の使い方を考えよう」(6年1・3組 家庭)
1組は服やゲーム等欲しいものがある場合、買うか買わないか、またその理由についてを討議し、本当に必要かどうかを考えました。その上で買いたいものを設定し品物の選び方や計画的なお金の使い方、気をつける所などを話し合いを通じて学びました。
3組は調理実習(野菜のベーコン巻・ポテトサラダ)の材料を買うにあたり、上手な買い方(分量、品質、値段)を考え、チラシの活用や親から情報を聞くとともにレシートの役割にも目を向けました。
(8) 「税と私たちのくらし」(6年2組 社会)
これまで学んだ歴史学習で昔から様々な税があったことを振り返りながら、現在の税の種類や複数の徴収先があること、その決められ方・使われ方についてグループで調べたことを発表しました。最後にゲストティーチャ―の小郡市役所税務課長から税金の具体的な使用方法や私たちの生活との関わりについて解説していただき、理解を深めました。
(9) 「電車に乗って 買い物をしよう」(あおぞら・かがやき学級 生活単元)
実際に本物のお金を使って必要なものを買い、品物の代金を正確に支払うことができるようになるとともに、お店の人への挨拶やコミュニケーション能力を養うことを目的に今回は電車に乗って買い物に行くリハーサルを行い、模擬の電車やお店で、切符の買い方や買い物を体験しました。
2.大原小学校の金銭教育の取組み
主題を「ものやお金を大切にする心 豊かな子どもの育成~大原プログラムに基づいた体験活動を通して~」とし、パワーポイントを使用して今までの授業の取り組みを発表しました。
インターネットや携帯電話の普及等子どもを取り巻く社会状況の変化や大原小学校児童の実態(落し物の多さ、携帯電話所有)を踏まえ「ものやお金を大切にする 心豊かな子ども」を目指し独自の教育プログラム「大原プログラム」を作成しました。同プログラムは3つの視点(心を育てる視点、消費者としての視点、生活者としての視点)から教科・道徳・特別活動・総合的な学習の時間において、地域と関わる体験活動を織り交ぜて金銭教育に取り組みました。具体的な取り組みとして学校と家庭が連携し「もったいない運動」を展開。節水・節電、ノートの使い方の工夫、鉛筆や消しゴムの丁寧な使い方等児童の工夫を全校に広めています。また、ベルマークや食品用トレイ、インクカートリッジ、アルミ缶のプルタブ、ペットボトルの蓋等を集めて無駄なく利用することにより車いすの寄贈やワクチン接種活動への寄付等も行っています。
このような取り組みにより、児童は、ものを最後まで使い切ることの大切さや不要になったものでも手を加えることにより再利用できること、資源には限りがあることを理解し「物を大切にする心」を育みました。今後も家庭との連携を図り、ものやお金を大切に使う実践力を身につけるとともに、働くことの喜びを考えキャリア教育にも繋げたいと結びました。

3.講演会
公開授業後、いちのせかつみ氏による保護者向け講演会「子ども達の生きる力と金銭教育」を開催しました。いちのせ氏は、日本人はお金の話は恥ずかしいことと考え避けてきたが、外国人から「エコノミックアニマル(利益を追求する動物)」と呼ばれるほど本当はお金が好きで、豊かで便利になった今こそ金銭教育が必要と説明されました。
金銭教育は1)知恵の習得(親・学校・地域)、2)躾(親)であり、昔は給料が現金だったのでお金が見え、働く人への感謝も生まれたが、現在は振込みとなりお金は見えず、働いていることも子どもには見えていないこと。よって働いた対価としての収入であることを子どもに伝え、買い物に連れて行って1個1個選ぶ理由(賞味期限・鮮度・値段等)を説明して買うことにより、子どもは見て覚えることができると話されました。このように、親と子が一緒に学ぶことが大切と説きました。
大事なことは貯めるのではなくどう賢く使うかで、おこづかいをいつからあげるかは子ども一人一人をしっかり見て、お金に興味を持った時に親子で話し合うことが肝要であると話されました。
また、「九州男児」というように、九州人は断ることをよしとしない風習があり、断ることができずに保証人になって自己破産というケースも多いため、是非「断る力」を身につけてほしいとも伝えられました。

4.プログラム
- 14:00~14:45
- 公開授業「ものやお金を大切にする 心豊かな子どもの育成~大原プログラムに基づいた体験活動を通して~」(全学年)
(1)ものをたいせつに「あおい じてんしゃ」(1年生 道徳)
(2)「町で生活し、働く人とのつながりを考えよう」(2年生 生活)
(3)物を大切に「えんぴつは なんさい」(3年1・2組 道徳)
(4)「もったいない 上手なお金の使い方を考えよう」(3年3組 学級活動)
(5)「ごみ減量・エコアップ大作戦」(4年生 総合的な学習の時間)
(6)「食と食をとりまく環境を考えよう~食は田んぼにあり~」(5年生 総合的な学習の時間)
(7)「金銭や物の使い方を考えよう」(6年1・3組 家庭)
(8)「税と私たちのくらし」(6年2組 社会)
(9)「電車に乗って 買い物をしよう」(あおぞら・かがやき学級 生活単元) - 15:00~15:40
- 開会行事
挨拶 小郡市立大原小学校 校長 林田 一徳
小郡市教育委員会 教育長 清武 輝
金銭教育の取り組み 小郡市立大原小学校 研究主任 永利 聡美 - 15:40~16:40
- 講演 「子ども達の生きる力と金銭教育」
講師:いちのせかつみ氏 - 16:40~16:50
- 閉会行事 挨拶 福岡県金融広報委員会 大西 洋






























































