金融教育公開授業
2013年度 金融教育公開授業
山梨県金融広報委員会
市川三郷町立上野小学校
金融広報中央委員会
山梨の実施報告
「金融教育公開授業 in 山梨(上野小学校)」(10月25日開催)
上野小学校は、甲府盆地の南端に位置し、周りを自然に囲まれ、古くから伝わる文化財が地域に多く残されています。「かしこく・なかよく・たくましく」を学校の教育目標とし、全校児童166名は学年の枠を超えて仲良く学校生活を送っています。
同校は、山梨県金融広報委員会から金銭教育研究校(24・25年度)の委嘱を受けて、今年度は「生き生きと学び合う子どもの育成を目指して」をテーマとして研究活動を進めてきました。
10月25日(金)に金融教育公開授業を開催しました。全学年で授業を公開し、研究発表の後、いちのせかつみ氏による講演会を実施しました。
▼ 参加者内訳:
1.公開授業
(1)「お金にへんしん」
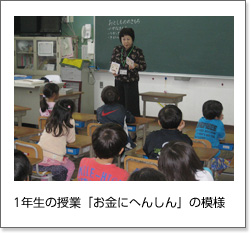 これまでの授業では、物を買うときはお金を払っていること、お金は働いて得るものであることを学びました。公開授業では、クラスの落し物箱の中を確認して、その落し物をお金に置き換えたり、落し物を擬人化してその気持ちを想像して発表したりしました。この結果、教室の中にはたくさんのお金に値するものが落ちていること、落し物が悲しんでいるはずであることに児童は気づき、お金や物を大切にすることを学びました。
これまでの授業では、物を買うときはお金を払っていること、お金は働いて得るものであることを学びました。公開授業では、クラスの落し物箱の中を確認して、その落し物をお金に置き換えたり、落し物を擬人化してその気持ちを想像して発表したりしました。この結果、教室の中にはたくさんのお金に値するものが落ちていること、落し物が悲しんでいるはずであることに児童は気づき、お金や物を大切にすることを学びました。
(2)「きゅうしょくとはたらく人たち」
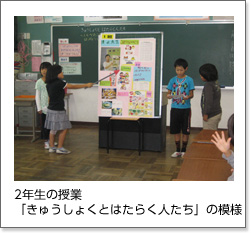 給食に関わって働く人たちのことを調べて、班ごとに発表しました。栄養職員や調理員のほか、運転員や用務員の方などから聞いてきた話が発表されるにつれ、給食を用意するためには多くの人が関わっていること、給食センターではたくさんの食材が取り扱われていること、お金がかかっていることを実感できたようでした。最後に、働く人たちへの感謝の気持ちと、自分たちが出来ることについて考えたこと(好き嫌いをしないように努力する、食器をきれいに片づけるなど)を各自でまとめました。
給食に関わって働く人たちのことを調べて、班ごとに発表しました。栄養職員や調理員のほか、運転員や用務員の方などから聞いてきた話が発表されるにつれ、給食を用意するためには多くの人が関わっていること、給食センターではたくさんの食材が取り扱われていること、お金がかかっていることを実感できたようでした。最後に、働く人たちへの感謝の気持ちと、自分たちが出来ることについて考えたこと(好き嫌いをしないように努力する、食器をきれいに片づけるなど)を各自でまとめました。
(3)「見直そうわたしたちの買い物」
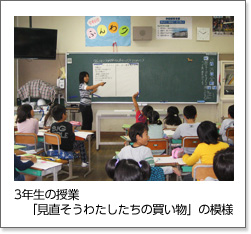 これまで、地域における生産や販売の現場を見学し、働く人や買い物に来る人にインタビュー調査を行ってきました。公開授業では、スーパーマーケットと直売所での販売方法や工夫の違いについて模造紙に書き出しました。また、買い物に来る消費者にとって、それぞれの工夫がもたらす良さを考え、発表しました。
これまで、地域における生産や販売の現場を見学し、働く人や買い物に来る人にインタビュー調査を行ってきました。公開授業では、スーパーマーケットと直売所での販売方法や工夫の違いについて模造紙に書き出しました。また、買い物に来る消費者にとって、それぞれの工夫がもたらす良さを考え、発表しました。
(4)「お母さんのせいきゅう書」
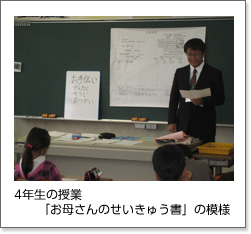 最初に家でどのような手伝いをしたか、そのときにどんな気持ちであったかを発表しました。その後、「お母さんのせいきゅう書」を読み、主人公の気持ちやお母さんの気持ちを考えながら、主人公への手紙を書きました。児童は、家族のために働くことの大切さや、感謝の気持ちを持つことの大切さを学びました。
最初に家でどのような手伝いをしたか、そのときにどんな気持ちであったかを発表しました。その後、「お母さんのせいきゅう書」を読み、主人公の気持ちやお母さんの気持ちを考えながら、主人公への手紙を書きました。児童は、家族のために働くことの大切さや、感謝の気持ちを持つことの大切さを学びました。
(5)「考えよう買い物と暮らし」
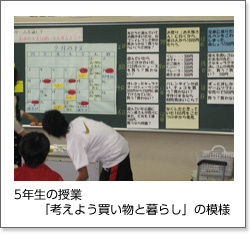 これまで計画的な買い物や賢い買い方について学習してきました。公開授業ではおこづかいゲームを行い、1か月間のお金の使い方について考えてみました。こづかいのもらい方を1)1か月分まとめて、2)3回に分けて、3)5回に分けての中から選び、サイコロを振って止まったところのカードに従います。カードによって自分で買うか買わないかを決められる場合と必ずお金を出し入れしなければならない場合があり、児童はそれぞれおこづかい帳に記帳していきました。最後に「自分のお金の使い方」と「お金の上手な使い方」について考え発表し合いました。
これまで計画的な買い物や賢い買い方について学習してきました。公開授業ではおこづかいゲームを行い、1か月間のお金の使い方について考えてみました。こづかいのもらい方を1)1か月分まとめて、2)3回に分けて、3)5回に分けての中から選び、サイコロを振って止まったところのカードに従います。カードによって自分で買うか買わないかを決められる場合と必ずお金を出し入れしなければならない場合があり、児童はそれぞれおこづかい帳に記帳していきました。最後に「自分のお金の使い方」と「お金の上手な使い方」について考え発表し合いました。
(6)「まかせてね今日の食事」
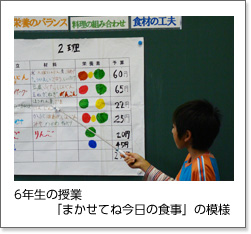 1食分の献立を班ごとに発表しました。この献立は、栄養バランス、色どり、食べる人の好みなどを考慮したり、予算を踏まえて食材選びをどのように工夫するかを相談したりして決めたものです。各班の献立の良さや、さらに工夫すると良いところについて気付いたことを話し合いました。最後に生徒各自が最も良いと考える献立とその理由についてワークシートに記入しました。
1食分の献立を班ごとに発表しました。この献立は、栄養バランス、色どり、食べる人の好みなどを考慮したり、予算を踏まえて食材選びをどのように工夫するかを相談したりして決めたものです。各班の献立の良さや、さらに工夫すると良いところについて気付いたことを話し合いました。最後に生徒各自が最も良いと考える献立とその理由についてワークシートに記入しました。
2.研究発表
金銭教育研究校の委嘱を受けて以来、全職員が各分野から「ものやお金・人との関わりの大切さ」を指導し、子どもたちの人間形成を目指していきたいと考え取り組んできたことが紹介されました。また、児童がお金を使う場面が多くないこと、みんなと協力して作業することを好む児童が多いことを踏まえて、実生活に即した体験的な活動を学校教育に組み入れるようにしてきたと発表がありました。
3.講演会
いちのせかつみ氏による「欲しいモノと必要なモノ」と題する講演が行われました。いちのせ氏は、コンビニエンスストアを題材に、売り手の工夫や、つい買いたくなる買い手の心情について解説されました。また、子どもの好きなお菓子や文房具を例示しながら、欲しいモノと必要なモノの違いや考え方を説明しました。
講演後、子どもたちからは、「お金を使うとき今本当に必要か考えたい」といった声があったほか、保護者からは、「身近なコンビニの話で子どもにも分かりやすく、家族で話し合える機会ができた」「子どもたちに考えさせる話し方で、今後子どもの買い物の仕方が変わることを期待したい」との声が聞かれました。
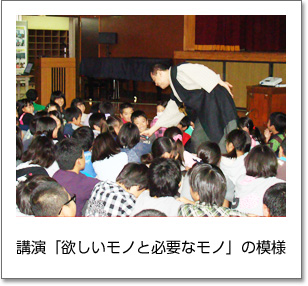
4.プログラム
- 13:30~14:15
- 公開授業
(1)「お金にへんしん」(1年生・学級活動)
(2)「きゅうしょくとはたらく人たち」(2年生・生活)
(3)「見直そうわたしたちの買い物」(3年生・社会)
(4)「お母さんのせいきゅう書」(4年生・道徳)
(5)「考えよう買い物と暮らし」(5年生・家庭)
(6)「まかせてね今日の食事」(6年生・家庭)
授業者:市川三郷町立上野小学校教諭 小林美和子、長澤はつみ、丹沢佳子、赤池智朗、澤谷雅紀子、伊藤美恵、伊藤千鶴、鈴木修
- 14:30~14:40
- 開会挨拶
市川三郷町立上野小学校校長 樋口勉
山梨県金融広報委員会事務局次長 安室実 - 14:40~14:50
- 研究発表 「生き生きと学び合う子どもの育成を目指して」~もの・お金・人との関わりの大切さに気づかせる金銭教育を通して~
発表者:市川三郷町立上野小学校教諭 赤池智朗 - 14:50~15:50
- 講演「欲しいモノと必要なモノ」
講師:いちのせかつみ氏 - 15:50~15:55
- 閉会挨拶
市川三郷町立上野小学校PTA会長 渡邉諭






























































