大学生のための 人生とお金の知恵
I. 人生のデザインとお金
1. これまでかかったお金
1) 高校を卒業するまでにかかったお金
-
あなたが生まれてから高校を卒業するまで、どのくらいお金がかかったのでしょうか?
-
「期間×金額」で考えてみてください。高校を卒業するまで、「期間」は月数でみると200か月を超えます(18年×12か月=216か月)。「金額」を仮に月5万円としても1千万円を超えます。月10万円とすると、2千万円を超えます。
-
-
1つの試算を挙げてみます。
高校卒業までにかかるお金(試算) 学校教育費脚注2 公立コース 約190万円 私立コース 約1,160万円 教育費以外脚注3 約2,210万円 - (出所)
- 文部科学省『子供の学習費調査』などを参考に作成
-
学校教育費と教育費以外の合計では、公立コースで2千万円台半ば脚注4、私立コースでは3千万円台半ばです(家庭教育費<習いごと、塾など>は、上表の試算には含めていません)。実際にかかったお金は、人によって異なりますが、「大きなお金がかかった」ことは実感できるのではないでしょうか。
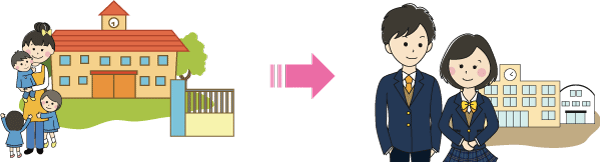
2) 大学を卒業するまでにかかるお金
-
大学に入学し、卒業するまでの4年間には、どのくらいのお金がかかるのでしょうか?
-
最も安い国立の自宅生で600万円弱、私立の自宅外生では1千万円強です。
大学4年間にかかるお金(試算脚注5) 自宅生 自宅外生(寮生除く) うち入学金・授業料等 国立 560万円 860万円 240万円 私立 文系 760万円 1,060万円 440万円 理系 920万円 1,220万円 600万円 (参考)医学部 2,740万円 3,040万円 2,420万円 -
なお、忘れがちな費用として、「機会費用」があります。大学に進学したことに伴い、入学金・授業料等のほかに、1千万円近い機会費用が発生しています。
-
機会費用とは、何かの選択をして、「機会を得た」=「別の機会を失った」ことに伴う費用です。逸失利益とも呼ばれます。
-
ここでは、「大学に進学する」選択をし、その機会を得ています。これは「大学に進学せず、就職して働く」機会を失ったことを意味します。仮に、高校を卒業して就職していたら年250万円の収入があったとすると、4年間では1千万円の機会費用が発生することになります。
-
-
機会費用も含めて、大学進学にかかる費用は、さまざまな能力を高めるための「投資」と考えられます。大学に進学することは、多額の投資をしていることになります。大学進学にかかる費用を上回る能力を身につけることが望まれます。
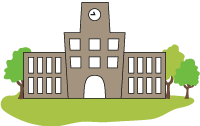
コラム1奨学金
-
すでにみたように、大学で学び、卒業するまでには、大きなお金がかかります(入学金・授業料、生活費など)。そのお金を、どのように賄っていますか?
-
大学や専門学校に進学した人の約半数は、何らかの奨学金を利用しています。
-
最も利用者が多いのが日本学生支援機構の奨学金です。大学生の約3人に1人は、同機構の貸与奨学金または給付奨学金を利用しています。貸与奨学金とは、返還(返済)する必要がある奨学金、給付奨学金とは返還する必要がない奨学金です。
-
給付奨学金は、2017年度に導入され、その後、拡充されてきています。最新の情報(利用条件ほか)は同機構のウェブサイトをご覧ください。
-
貸与奨学金には、第一種と第二種があります。第一種は無利息です。第二種は利息付です(大学在学中は無利息)。いずれも、卒業の半年後(7か月目)から毎月、口座引落しで返還することになります。
| 貸与奨学金=返還が必要 | 給付奨学金 返還が不要 |
|
|---|---|---|
| 第一種=無利息 | 第二種=利息付 | |
返還の例(定額返還のケース)
| 借りた額 | 返す額 | 返す期間 | 毎月の返還額 |
|---|---|---|---|
| 2,592,000円 | 2,592,000円 | 15年(180か月) | 14,400円 |
| 借りた額 | 返す額 | 返す期間 | 毎月の返還額 |
|---|---|---|---|
| 3,840,000円 | 金利0.905%の場合 4,216,365円 うち利息分 376,365円 |
20年(240か月) | 17,568円 |
*金利0.905%は、2023年3月貸与終了者への適用金利(利率固定方式)。
-
23歳から返還を始めると、これらの例では返還が終わるのは38歳や43歳です。繰り上げ返還も可能です。
-
返還できずに延滞した場合、延滞金利(年率3%)が課されます。3か月以上延滞した場合、信用情報機関に登録され、クレジットカードを作れなくなったり、住宅ローンを組めなくなったりします。延滞期間が長くなると、延滞金利によって返還すべき額が大きくなっていきます。
-
経済的理由により返還が困難な場合、月々の返還額を1/2または1/3にしてくれる減額返還制度があります。返す期間は長くなりますが、第二種の利息の支払額は変わりません。返還が困難な事情がある場合、期限を先延ばししてくれる返還期限猶予制度もあります。猶予してもらうためには毎年申請する必要があります。猶予期間は原則として通算10年が限度です。
-
第一種奨学金を借りた人には、定額返還方式のほかに、所得連動返還方式(卒業後の所得に応じて返還額を毎年見直せる方式)も選べるようになっています。
-
3か月以上延滞している人は12.8万人です(2021年度末)。返還者に占める割合は2.7%です
-
貸与奨学金は、進学するために借りているお金です。社会人となってしっかり収入を得て、奨学金を返還できるよう、学生時代に能力を高めることに役立てましょう。
- (出所)
- 本コラム中の日本学生支援機構の奨学金に関する記述は、同機構のウェブサイト、「奨学金事業への理解を深めていただくために(令和5年5月)」などを基に作成
脚注
- 2
-
「学校教育費」のうち、「公立コース」は幼稚園から高校まですべて公立、「私立コース」はすべて私立に通った場合の試算です。幼稚園は3年として計算しています(文部科学省『令和3年度子供の学習費調査』を基にした試算)。
- 3
-
『これであなたもひとり立ち』のワーク2「私の命を育んだお金はいくら?」は、生まれてから高校を卒業する18歳までの間に、どのくらいのお金がかかったのかを計算するワークです。同書の教師用『指導書』に、参考計数を掲載しています。上表の「教育費以外」の試算は、同書(2023年2月版)を参考にした試算結果です。なお、「教育費以外」の内訳は、食費約520万円、住居費約440万円、こづかい・交際費約360万円、通信・交通費約320万円、教養娯楽費約180万円、水道光熱費約140万円などとなっています。
- 4
-
学校教育には、税金もかかっています。たとえば、公立学校の児童・生徒1人に、小学生では約98万円、中学生では約112万円、高校生(全日制)では約106万円が1年間に支出されています(2020年度)。これらを合計すると、小・中・高の12年間で1千万円以上の税金がかかっていることになります。
- 5
-
「入学金・授業料等」は、『私立大学等の令和3年度入学者に係る学生納付金等調査結果』(文部科学省)に基づいて試算。「入学金・授業料等」以外の支出は、生活費。『学生生活実態調査』(全国大学生活協同組合連合会、2019年10〜11月実施)に基づいて、自宅生で約320万円、自宅外生で約620万円と試算。






























































