わかりやすい社会保障制度
II.社会福祉
社会福祉制度とは、児童、母子、心身障害者、高齢者など、社会生活を送る上でハンディキャップを負った人々に対して、公的な支援を行う制度のことです。支援を必要とする社会的弱者が心身ともに健やかに育成され、能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように支援するとともに、社会福祉は救貧・防貧の機能も果たしています。対象者別に社会福祉についてみていきましょう。
1.児童福祉
1)保育所
保育所は、親の就労や病気などの事情で家庭で保育することのできない乳幼児を、保護者に代わって保育することを目的とする施設で、児童福祉法に基づく児童福祉施設の1つです。対象となるのは0歳から小学校入学前までの児童です。
保育所の入所手続きは次のような仕組みで行います。
図表1:保育所入所の仕組み
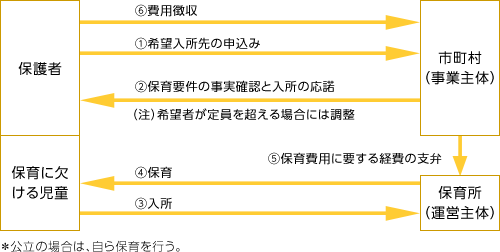
出典「社会保障入門2010」社会保障入門編集委員会、中央法規出版
保育料は、児童の年齢と保護者の所得から算定されます。国が基準額を示していますが、保護者の負担を軽減するために多くの市町村は財源を投入し、国の基準よりも軽減した保育料を設定しています。
保育所は全国で約23,000か所あり、保育所を利用している児童数は約208万人です(平成22年4月現在)。共働き世帯の増加や核家族化の進行により、保育所の需要は高まっており、保育所の入所を希望している待機児童数は、都市部を中心に全国で約26,000人います(平成22年4月現在)。
近年、増大する保育需要に対応するために、定員の弾力化、小規模保育所の設置促進、設置基準の弾力化、短時間勤務保育士の導入拡大など、様々な規制緩和が行われています。また、延長保育、夜間保育、休日保育、子育て家庭に対する相談支援、一時保育などの提供が進められています。
なお、上記のような認可保育所のほかに、企業が従業員のために設けた事業所内保育施設、ベビーホテルなど、認可外保育所といわれる施設があります。
また、就学前の子どもの教育・保育ニーズに対応する新たな選択肢として「認定こども園」の制度が平成18年10月からスタートしています。幼稚園と保育園の良いところを活かしながら、その両方の役割を果たすことが期待されています。
2)児童に関する手当
(1)子ども手当
次代の社会を担う子どもの1人ひとりの育ちを社会全体で応援すること、子育ての経済的負担を軽減し安心して出産し子どもを育てられる社会をつくることを目的として、平成22年4月から、子ども手当の制度が始まりました。
子ども手当施行以前に行われていた類似の制度である児童手当には所得制限がありましたが、子ども手当には所得制限がありません。子ども手当の支給を受けるためには、住所地の市区町村への申請手続きが必要です。
平成22年度は、中学校修了まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)の子ども1人につき、月額1万3000円が父母等に支給されました。子ども手当の支給を受けた父母等は、子ども手当の趣旨に従って子ども手当を使用する責務があります。
子ども手当の制度に関しては財源の確保が課題となっており、手当の金額については流動的な状況です。
(2)公立高等学校の授業料無償化・高等学校等就学支援金
家庭の状況にかかわらず、すべての高校生が安心して勉学に打ち込める社会を作ることを目的として、公立高等学校の授業料が、平成22年4月から、無償化されました。無償化されるのは授業料のみで、入学金や教科書代、修学旅行費等、授業料以外の学費は無償とはなりません。所得による制限はありません。
同様の趣旨から、国立・私立高等学校(全日制、定時制、通信制)等に在学する生徒については、月額9,900円を限度として高等学校等就学支援金が支給されます。所得による制限はありません。
3)児童相談所
児童相談所は、児童福祉法に基づいて設置された、児童福祉の第一線の機関です。都道府県、指定都市に設置が義務付けられており、全国で205か所あります(平成22年5月現在)。
児童相談所には、ソーシャルワーカー(児童福祉司、相談員)、児童心理司、医師(精神科医、小児科医)、その他の専門職員がいて、児童に関する相談業務、専門的な調査・診断・判定、それに基づく児童・保護者などへの指導、一時保護、児童福祉施設への入所措置などを行っています。
児童に関する相談の種類には、(1)障害相談(障害のある児童に関する相談)、(2)育成相談(しつけ、性格行動、適性、不登校、教育その他児童の育成上の相談)、(3)養護相談(保護者の病気、家出、離婚などによる養育困難児、棄児、被虐待児、被放任児など養育環境上問題のある児童に関する相談)、(4)非行相談(窃盗、傷害など問題行為のみられる児童に関する相談)、(5)その他の相談などがあります。近年は重大な児童虐待事件が跡を絶たず、全国の児童相談所における児童虐待に関する相談対応件数も増加を続け、平成20年度には4万件を超えています。
4)地域における児童の健全育成・養護を必要とする児童の自立支援
児童が心身ともに健全に育成されるためには、地域における遊びの場の確保や地域の活動が必要です。そこで、地域の組織活動(子ども会、親の会など)への支援、遊び場の確保のための児童厚生施設(児童館・児童遊園など)の整備、放課後児童クラブの育成などの施策が実施されています。
保護者がいない、いても保護者に養育させることが適当でないなどの理由により、家庭での養育が困難な子どもについては、乳児院(1歳未満の児童が対象)、児童養護施設(1歳以上の児童が対象)が整備されています。また、「里親」家庭などへの委託が行われます。
非行児童については児童自立支援施設、情緒障害児については情緒障害児短期治療施設により、健全な育成が図られています。
5)子ども・子育てビジョン
「子ども・子育てビジョン」というのは、今後の子育て支援の方向性についての総合的なビジョンです。平成22年1月に閣議決定されました。「子ども・子育てビジョン」では、「社会全体で子育てを支える」、「希望がかなえられる」という2つの基本的な考え方に基づいて、目指すべき社会への政策4本柱と12の主要施策を掲げ、数値目標も併せて提示しています。その取り組みの前提として従来の「子育ては家族が担う」という考え方から、「社会全体で子育てを支える」という考え方への転換を打ち出しています。
子ども・子育てビジョン(PDF 615KB)(文部科学省HPへリンク)
政策4本柱とは、「子どもの育ちを支え、若者が安心して成長できる社会へ」、「妊娠、出産、子育ての希望が実現できる社会へ」、「多様なネットワークで子育て力のある地域社会へ」、「男性も女性も仕事と生活が調和する社会へ(ワーク・ライフ・バランスの実現)」の4つです。






























































