はやわかり金融商品取引法&金融商品販売法
金融商品を取引するときの注意点
1.金融商品を取引するときの注意は?
金融商品取引法では、業者が一般の投資家(アマ)を相手に、販売・勧誘・契約を行うときに守るべきルールが定められています。こうしたルールを業者が守っているかどうかは、私たちが自分で確認し、守っていない業者とは取引しないようにしましょう。
業者には内閣総理大臣への登録が義務づけられています。
登録業者かどうかを、金融庁のホームページで確認しましょう!
登録業者だからといって取引の安全性が保証されているわけではありません。取引しようとしている業者の勧誘方針や財務状況などを確認しましょう。
業者は、顧客の知識や経験、資産状況、購入目的等を確認したうえで、顧客に合った商品をすすめることが義務づけられています(適合性の原則)。
業者から投資知識や投資経験等を質問されたときには、正しく回答するようにしましょう。背伸びや見栄は禁物です。
「適合性の原則」に違反する行為とは・・・
- たとえば
- 投資知識や経験が全くない人に、そのことを知りながら、ハイリスク型の投資信託をすすめること。
- 80歳代の高齢者に、20年後に支払が始まる年金商品をすすめること。
業者の次のような行為は、顧客の投資判断を誤らせるものとして、禁止されています。
| 真実ではないことを言って購入をすすめること。(虚偽の説明) | 「必ず上がります」とか「絶対に○○になる」と断定することや、そう思わせるような表現を使って購入を誘うこと。(断定的判断の提供) |
| 頼んでもいないのに自宅や勤務先に押しかけてきたり電話をかけてきて、取引を勧誘すること。(不招請勧誘)
※当面、外国為替証拠金取引(店頭取引)のみ。 |
「いりません」とはっきり断ったのに、しつこく取引を勧誘すること。(再勧誘) ※当面、金融先物取引のみ。 |
迷惑と感じる時間帯に自宅に押しかけてきたり電話をかけてきたりして、取引を勧誘すること。
※原則として法人顧客を除く。商工ファンドなどのみ。
迷惑行為に出会ったら、はっきりと「ノー」といいましょう。

2.契約の内容を説明する書面の義務
業者は、契約前に、契約の内容を説明する書面(※)を顧客に必ず渡すことが義務づけられています。
書面には、次の事項を必ず記載することが義務づけられています。
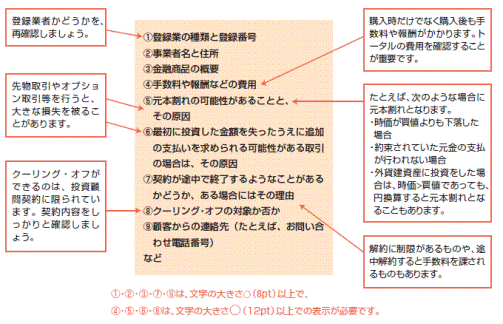
※上記の内容をすべて記載している場合に限って、目論見書(もくろみしょ)で代用することが認められています。目論見書とは、有価証券の募集や売出しに際して、投資家に交付が義務づけられている文書です。投資信託の場合は、投資信託説明書とよぶ場合があります。
業者は、契約成立後、すみやかに、契約内容を書いた書面を顧客に渡すことが義務づけられています。

こんなことに気をつけましょう
- 取引は、きちんと理解してからにしましょう。
- 交付された書類は勧誘や取引の記録や証拠となりますから、必ず保管しましょう。
- 取引を事業者に任せっきりにすることは絶対にしてはいけません。






























































