金融教育フェスタ
金融教育フェスタ2017
先生のための金融教育セミナー


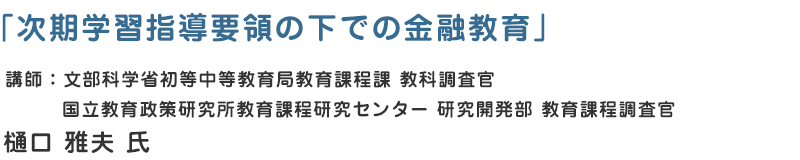
「次期学習指導要領の下での金融教育」
講師:文部科学省初等中等教育局教育課程課 教科調査官
国立教育政策研究所教育課程研究センター 研究開発部 教育課程調査官
樋口 雅夫 氏
小学校、中学校においては、本年の3月に新しい学習指導要領が公示されました。高等学校においても、今年度中の公示を目指して作業を進めているところです。私ども文部科学省としては、現場の先生方お一人お一人にこの新しい指導要領の理念や趣旨をお伝えしていくことが大事だと考えています。
近年、情報化やグローバル化といった社会的な変化が人間の予測を超えて進展しています。これからの社会を生きる子どもたちは、このような社会の変化と無関係ではいられません。例えば、中学校社会科の学習指導要領の解説では、公民的分野で「財やサービスの取引は貨幣を通して行われていることを理解できるようにするだけではなく、近年ではICTの発達などにより、フィンテックと呼ばれるIoT、ビッグデータ、人工知能といった技術を使った革新的な金融サービスを提供する動きが多く見られ、様々な支払い方法が用いられるようになってきていることを理解できるようにすることも必要である」という記述があります。フィンテックの細かなシステムを学ぶことを目指しているのではなく、このような社会の中で私たちは何ができるのか、何をしなければいけないのかを考えることこそが重要です。
「主体的・対話的で深い学び」の視点に立って授業を改善するとよりよい授業ができるのではないかということで学習指導要領の改訂が進んでいます。最近、「深い学びとは何ですか」と問われることがあります。その答えは一つではありません。子どもたちが知識を相互に関連付けてより深く理解したり、物事を比較したりしながら、「ああ、なるほど。そういうことだったのか」という深い学びにつなげていくということが大事です。また、今まで自分の視点だけで見ていたが、友だちの視点からも物事を見ることができるようになったとか、自分以外の人の願いや思いを捉えた上で自分の考えを形成することができる、情報を精査して根拠に基づいて自分の考えを形成し表すことができることも深い学びの姿だと思います。問題を見出して解決策を考えたり、授業後に新たな問題を発展的に見出して、それを生かしていこうとすることも深い学びです。
授業では、何かを調べたりまとめたりしてインプットする部分が多くなります。それだけでなく、子ども同士で協働してさらに意見を再構築し、それをアウトプット、つまり発信することも大切です。発信というのは、社会への提言だけでなく、クラスの中で発表する、壁新聞にまとめるなど、様々な方法があります。このような活動のサイクルを繰り返すことによって、知識がより深く身に付き、金融が社会の中で自分の生活にどう生きるのかを深く考えることにもつながるのではないかと期待しています。
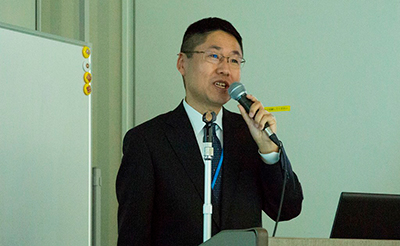
基調講演の模様
講師プロフィール
広島経済大学講師を経て現職。
「学校における金融教育推進のための懇談会」 高等学校分科会委員として「学校における金融教育の年齢層別目標」
および『金融教育プログラム』全面改訂版作成に協力。
- 主催:
- 金融広報中央委員会・長崎県金融広報委員会
- 後援:
- 文部科学省、金融庁、消費者庁、日本銀行、日本PTA全国協議会、長崎県、長崎市、長崎県教育委員会、長崎市教育委員会、長崎県小学校長会、長崎県中学校長会、長崎県高等学校長協会






























































