金融教育フェスタ
金融教育フェスタ2017
先生のための金融教育セミナー


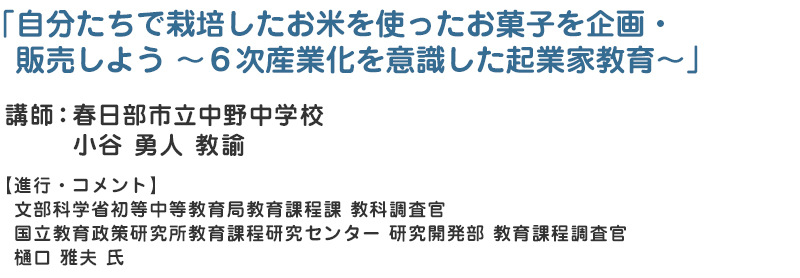
「自分たちで栽培したお米を使ったお菓子を企画・販売しよう ~6次産業化を意識した起業家教育~」
春日部市立中野中学校 小谷 勇人 教諭
【進行・コメント】
文部科学省初等中等教育局教育課程課 教科調査官
国立教育政策研究所教育課程研究センター 研究開発部 教育課程調査官
樋口 雅夫 氏
<実践発表>
現在、中学校3年生の主任と担任を持っており、社会科教諭として日々勉強しながら色々な活動をしています。中でも起業家教育に非常に大きな可能性を感じており、今日はそれに関わる実践をお話しします。「自分たちで栽培したお米を使ったお菓子を企画・販売しよう」ということで、起業家教育の視点に6次産業化というものをプラスした取り組みです。
日本の起業率は諸外国と比較して低く、子どもたちに聞いても、将来、起業して社長になることを選択肢に入れている子は多くありません。その理由は、メリットよりもデメリットのほうが大きい、周囲の理解が得られない、ビジネスチャンスが思いつかない、成功する自信がないなど色々ありますが、教育現場においては、起業家教育を通して自己肯定感を高めることが大事だと考えました。
社会科の地理的分野で日本の食料自給率の話をしますが、子どもたちにただ数字を見せてもあまり実感を持ちません。もっと地域の生の声を聞き、日本の農業の置かれた現状と向き合い、自分たちができることを真剣に考える必要性があると感じました。そこで、産業学習に子どもたちが主体的に取り組む手立てとして、6次産業化と起業家教育を組み合わせ、中学校から新商品をつくるという事業計画を立てることを考えました。総合的な学習の時間を使い、それぞれの学習活動がスパイラル状につながって探究的な学習となるよう、1.地域の農家の支援を受け、地元の名産である農産物をつくる、2.企業を経営している方にお話を聞いたり、自分たちの考える新商品について講評を受けたりする、3.実際に生まれた商品の販売活動を行う、4.新商品開発プロジェクトの総括をする、ということを1年間にわたって行いました。
結果として、地域に対する子どもたちの誇りや愛情を大いに喚起することができ、1年間という長いスパンで学年経営に総合的な学習の時間を位置づけることができました。一方、課題として、企画した商品を完全に商品化するところまではたどり着くことができなかったという点があります。事前の打ち合わせをより密に重ねておく必要があると感じました。また、社会科では地理的分野の産業学習とリンクさせることができましたが、1年間の長いスパンでやるからこそ、他教科の内容を理解し、カリキュラムマネジメントを行う必要性があると感じました。
<ワークショップ>
「自校で子どもたちに新商品を開発させるとしたら、どのような手立てや内容があるか」について、まずは各自で地元の環境や生徒の実態を踏まえて考え、さらにグループで共有し、その中からアイディアを絞って練り上げていきました。各グループの発表では、地元の特産品を使った様々な商品のアイディアや子どもたちが行うプロモーション方法に関する案などが発表され、大変盛り上がりました。
<コメント>
樋口先生より次のようなコメントがありました。
新しい学習指導要領では育成を目指す資質・能力について述べていますが、小谷先生も、この起業家教育で目指すのは、子どもたちの自己肯定感を高めることだと明確にされていました。人には様々な生き方があり、起業という生き方もあれば、企業に勤めて定年まで働くという生き方もある、また他の人にはない自由な発想が未来を開くこともあるということを子どもたちに気付かせることが学校教育であり、今回の起業家教育であると思います。子どもたちは大人が思いつかないような発想をする可能性があります。それを先生が、あるいは周りの友達が認めていく中でそれぞれの自己肯定感が高まっていくのだと思います。
未来をつくっていくのは子どもたち自身ですが、そのためには実現可能性を検討することも必要です。いくらいい発想であっても、実際に起業できるのか、あるいは経営し続けることができるのかという視点が現実的には求められます。こうしたことは高等学校を卒業するまでに身に付けるべき資質・能力ですが、高等学校の先生方は、ご自身の専門分野ではないところについては他教科の先生や外部講師の力を借りることで、より精度の高い学びが実現できるのではないかと思います。

実践発表・ワークショップ2の模様
- 主催:
- 金融広報中央委員会、長崎県金融広報委員会
- 後援:
- 文部科学省、金融庁、消費者庁、日本銀行、日本PTA全国協議会、長崎県、長崎市、長崎県教育委員会、長崎市教育委員会、長崎県小学校長会、長崎県中学校長会、長崎県高等学校長協会






























































