金融教育フェスタ
金融教育フェスタ2017
先生のための金融教育セミナー
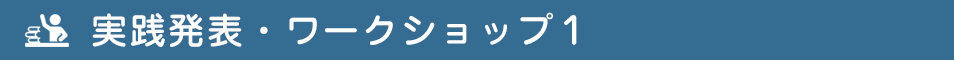

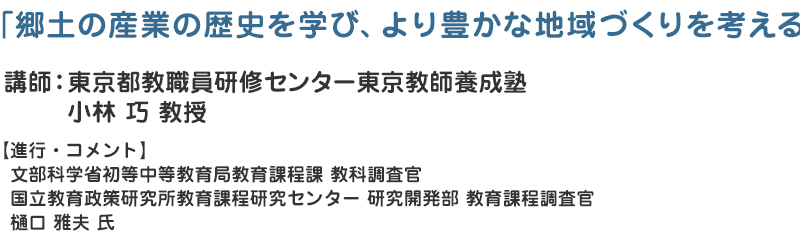
「郷土の産業の歴史を学び、より豊かな地域づくりを考える」
東京都教職員研修センター東京教師養成塾 小林 巧 教授
【進行・コメント】
文部科学省初等中等教育局教育課程課 教科調査官
国立教育政策研究所教育課程研究センター 研究開発部 教育課程調査官
樋口 雅夫 氏
<実践発表>
私はこれまでに三つの学校で校長を経験しました。本日はその三つの学校で「お金を通して社会を見る目や考える力を育てる」ことを目標に行った授業実践を中心にお話させて頂きます。
一つ目の小学校では、地元の商店街にお店を出そうということで、4年生の総合的な学習の時間を使い、企画会議、市場調査、融資交渉、プレゼンテーション等の授業実践を行いました。この学習活動により、校内の教師たちの金銭教育への理解と教育的な効果が得られました。子どもたちの学習意欲や課題を主体的に追究する力が向上し、学ぶ力が教材によって大きく伸びることを実感できた研究です。ただ、研究実践者の高い指導力があっての授業実践だったため、「素晴らしいが自分には同様の実践は難しい」という声も聞かれ、学校全体の教育課程に十分に反映されないという課題が残りました。
この課題を受けて、二つ目の小学校では学校全体の研究に広がるように、特に社会科、生活科を中心に授業改善に取り組みました。金融教育では、家庭科との連携も重要ですので、家庭科での授業実践も組み込みました。結果として、金融教育が目指す「自立するための力」や「社会と関わる力」の育成につながることに手応えを感じました。
三つ目の八王子市立第二小学校では、より充実した研究をすることができました。小学校で子どもたちに社会を見る目や考える力を培うことが、中学校、高等学校以降の金融教育につながっていくということを実感しました。金融教育の視点を「見通す力」、「自己決定力」、「社会と関わる力」、「コスト意識・経済感覚」、「勤労意欲」、「ものを大切にする心」の六つとしました。社会科と生活科を中心に授業実践を展開したため、これらの中でも「社会と関わる力」や「コスト意識」を特に重視しました。生活科では繰り返し体験することがとても大切です。町で働く人を紹介する活動があるのですが、一回ではなく何度も見学に行きます。その結果、地域との関わりが少しずつ深まり、社会と関わる力が育っていきました。また、これが基礎となって社会科の学習につながりました。
金融教育を進めることによって、子どもたちが、将来を見通しながら主体的に考え工夫し努力する態度が身に付きました。金融教育というと、教育現場では「また新しいことをしなければいけないのか」と負担に感じる先生方もいらっしゃると思いますが、金融教育には大事にするポイントがあります。まずは、そのポイントを日頃行っている授業の中に取り入れて「少し授業改善をしてみようかな」という気持ちで取り組んでもらえればよいと思っています。
<ワークショップ>
八王子市立第二小学校4年生の社会科で行った内容を実際に体験しました。
「八王子は明治時代、織物で栄えており、外国人も多くの時間とお金をかけて生糸を買いに来ていた。外国からも買いに来るほどなのだから、生産量がもっと増えていいはずなのに、生産量のグラフを見るとそれほど増えていない。自分だったら生産量を増やすためにどんなことをするだろう」という課題を、KJ法を使って思考を可視化しながらグループで話し合いました。参加者からは、「生産量を増やすために養蚕農家を増やす」とか「外国から技術を導入して規模の大きい工場をつくる」という意見のほか、「『世界の八王子へ』というタイトルを付けて、世界的な視野で付加価値を高めていく」という意見も出されました。
また、まとめの中で、小林先生から、「子どもたちが意見を出し合った後、教師が評価をすることが多いが、一旦、評価をしてしまうことでそれ以上話し合いが深まらない。そこで、あえてこのタイミングでは評価をせずに全体の話し合いに進み、教師が目当てに向かって調整しながら資料や情報を提示し、子どもたちがそれを基に確認し合ったり、話し合ったりするという展開とした」という話や「机間指導をする教師が、なぜそう思ったのか、そこから何がわかるかという質問を子どもたちに投げかけることで、子どもたちの考えがグループの中で深まり、対話的な学びが充実していく」という話がありました。
<コメント>
樋口先生より次のようなコメントがありました。
小林先生の実践のポイントは、「自由な発想」ということだと思います。子どもたちは、まず個人で、そしてグループで思ったことを自由に書き込む、あるいは発表するということを行っていました。子どもたちの発想を大事にし、そこから教師が本当に伝えたいことに迫っていた点が効果的だったと思います。また、KJ法を使うことで、教師が細かく指導しなくても、子どもたちが自分で発想をつなげていくことができていました。その結果、4年生の子どもたちが、5年生で学ぶ価格や費用にまで着目して考えることができたのだと思います。子どもたちの理解が少し足りなくても、教師がすぐに訂正したりせずに見守ることで、子どもの力を利用して深い学びにつなげていくという工夫がなされていました。
自由な発想で子どもたちが話をし、自由な発想で教師が教材研究をする中で、教材自体のつながりや金融教育の視点とのつながりもでてくるのではないかと思います。小林先生からは、机間指導等について具体的なテクニックのお話もありました。こうしたことをこれからの先生方の授業に生かしていただければと思います。

実践発表・ワークショップ1の模様
- 主催:
- 金融広報中央委員会、長崎県金融広報委員会
- 後援:
- 文部科学省、金融庁、消費者庁、日本銀行、日本PTA全国協議会、長崎県、長崎市、長崎県教育委員会、長崎市教育委員会、長崎県小学校長会、長崎県中学校長会、長崎県高等学校長協会






























































